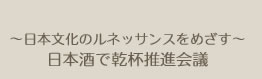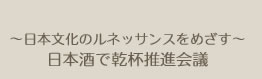|
その酒蔵は田んぼの真ん中にあった。小田急線で新宿から50分、宅地化が進む農村の一角に酒造りのタンクが聳え立つ。2016年2月の寒い日、私が代表をしているNPO法人「良い食材を伝える会」の一行が、この酒蔵を訪れた。この会は“食から日本を考える”との大テーマの下、毎月2回ほどのペースで勉強会を開いていてもう10年が経つ。時に食や農の現場を訪問する出前授業を行っていて、今回もその一環であった。
訪ねた酒蔵の名前は「泉橋酒造」、社長は橋場友一さんという。創業は江戸時代末期の安政四年、1857年である。現在の社長は六代目である。いま48歳、慶応大学卒のイケメン社長であった。
酒蔵の中を案内して頂きながら、私がまず感じたのは杜氏がいない、ということだった。私はかつて灘のある大手の酒造メーカーを取材したことがある。その時は、酒蔵の中で多くの杜氏たちが働いていた。皆が一斉に食卓につく夕ご飯の時などは壮観であった。その記憶が残っていた私は、いかにも古かった。
現在はこうじ造りから仕込みまで、工程は客観的、科学的なデータに基づいている。年間100日という決して効率的とは言えない労働者である杜氏はいない。1人の役員の名刺に、わずかに副杜氏の肩書が残っているだけである。
しかし橋場社長は、その機械化の時代にあっても、あえて手造りの良さを残そうとしていた。代表的なのはこうじを作るには、全量木製のこうじ蓋を使う。そして大切なこだわりは、原料米である。酒蔵をとり巻く田んぼで生産されるコメで造る酒、橋場社長は“酒造りはコメ作りから”の信念の下、酒米栽培から精米、醸造までを一貫して行ってきた。まずコメと向き合うこと、そして田んぼがあるから蔵がある、という考え方が原点だと、橋場社長は言う。
農薬を減らしたコメ作りのため、季節になると、泉橋酒造のトレードマークであるトンボが田んぼを飛び回る。大都会のすぐそばに、こんな酒蔵があった。
|