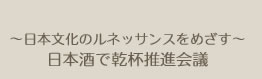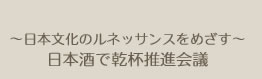|
父は97歳の冬に肺炎で入院、あっという間にあの世に旅立った。
死の前日、「どうですか」と回診に見えた医師に「え、なんなら熱燗を一杯飲ませてください」と冗談をいった。
居合わせた看護婦さんも同室の患者さんも大笑いしたというが、そんなことは叶えられずあっけない幕切れとなった。
父の酒は楽しかった。「心地よい気分」になる酒が常だった。
晩酌もほどほど、憂さ晴らしとかやけ酒といった飲み方はしたことがない。そんな時は寄席や芝居を見に行った。泥酔したのはたった一度、親戚の結婚式で杯を重ねすぎて正体をなくした、が、それとてまだ若い時の話だ。
父はなんと上手な酒を飲んでいたのだろう、と今でも私は思っている。
私の記憶では我が家で酒が切れたということは一度もない。四季を通して、酒との縁は深く、暮らしのメリハリの中にいつも辛口の酒が加わっていた。人の輪や付き合いに、料理や母や祖母の化粧品に、事あるごとに酒は濁る間もなく流され補充されていた。
わたしとて小学校一年生の時からお酒をたしなんでいた。
なにしろ、50年も前の東京の冬はとても寒かった。木枯らしも吹いたし、雪も降った。手足に霜焼けも出来たし、私などは寒冷蕁麻疹の常習犯だった。
「これを飲んで行きな」祖母が通学前に差し出したのはおちょこ一杯の日本酒だった。日本酒はいかにも味がそっけなく子供向きではないが飲みにくいということはなかった。日本酒のにおいは生活の中で馴染んでいたせいだろう。
祖母は体が温まるようにと考えてくれたのだ。ぐいと飲めば一息だ。
父も熱燗のほうがいいんじゃないか、などと言っていたから、止める気などは全く無かったのだ。何しろ、この父は始業式を初日といい、終業式を楽日というくらいだから学校の教育などに興味もなかったのだ。
その一杯の酒はやはり体を芯からあたためた。ぽっと頬を染めたかどうか覚えていないが、だから酒の訓練は自然体として身についてしまった。
父ともよく杯を重ねた。死ぬ前に本当に飲みたかったのだろうな、と思うだけで今も胸が痛い、一緒に飲んであげたかった。
|