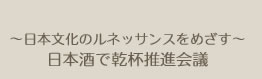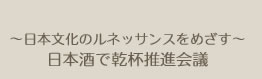|
人生の体験は飲酒から始まった。
大学に入って悪友と知己になり、生まれて初めて酒に「酔う」ことを知った。とても気持ちがいいのに、何か悪事を働いているという後ろめたさを味わった。この新鮮で微妙な体験は無垢な少年時代に決別させた。「酔う」ことで目覚めた官能は、私がそれまで育てられてきた素直さを歪め、複雑な人間にしたと思った。新世界の発見である。平凡な日常に縛られた人間が個人で体験できる事柄は極めて限られている。読書や映画は所詮、ヴァーチャルで理性的な体験である。心身に染渡る体験はスポーツを除けば、おそらく恋愛であろう。しかし、酒に酔った人類が体験した喜びや罪は、恋愛やスポーツに劣らず広く、深い。
様々な種類の酒を様々な国で飲み、歳を重ねるうちに、日本酒が洋酒や紹興酒よりも味わい深くなったのは何時ごろからだろうか。私の映画音楽のパートナーだった今は亡き武満徹がある日突然、酒は日本酒だといった。彼がニューヨーク・フイルハーモニー交響楽団のために、琵琶と尺八のための協奏曲『ノヴェンバー・ステップス』(1967年)を作曲したころだったろうか。我々戦後世代もアメリカやヨーロッパ文化の呪縛から脱して、ようやく日本と本気で向かい合うようになっていたのだ。八十歳になった今は一合の晩酌が負担になって五勺になっている。浅酌という言葉があるが、ワインやウイスキーでは似合わない。今年の正月も箱根駅伝をテレビで観戦した。こんな時の浅酌ほど心地よいものはない。私には昭和二十五年の駅伝で2区を走った経験がある。テレビは東洋大学の柏原竜二選手が驚異のピッチで箱根山を登り切っていた。電話が鳴った。母校の惨敗を嘆くはずの友人が、私と同年に山登りを走った山田俊氏の死去を伝えてきた。山田俊氏は、当時1500メートルの日本記録保持者で我々のコーチだった中村清氏が保持していた記録を書き換えたエースであった。六十年以上も昔のことだ。浅酌が深酒になっていた。弔い酒をなんと呼べばいいのか。
|