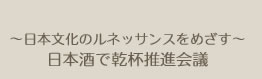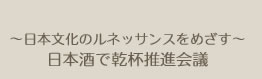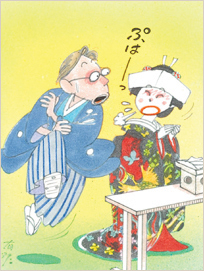 |
| イラスト:さとう有作 |
相手に酒をすすめるときに、ごく何気なく「もう一献(いっこん)いきましょう」などと言う。
古く、酒のことを女房言葉では「九献(くこん)」とも言った。江戸期までは、よく使われた言葉である。
では、その「献」とは何を意味するのか。もちろん、料理の「献立」とも相関するが、本来の意は、「酒肴(しゅこう)一献」にある。つまり、簡素な肴をだして一盃の酒をすすめ、それを納めるのを一献とするのだ。その酒肴をとりかえて三回、つまり三献で接待するのが、古くは正式な作法とされた。これを「式三献」という。そのとき、盃の酒を三口(三度)で飲み干す。
「ひと杯の酒をのむを一度といひ三度のむを一献といひき、なみゐたる座にてさかづきを一たびめぐらしのむをば一巡といへり。さてものゝ儀式に、うるはしくのむは三度と三献とにぞありける」(「松の落葉」『古事類苑 飲食部』)
三度とは、三口。それは、慎重を期する意。三つの杯(盃)を三口ずつで飲むのであるから、つまりは「三三九度」。この三三九度の盃事(さかずきごと)は、契約儀礼となる。特定の人と人との間で取り交わす儀礼として伝えられた。
式三献は、中世から近世を通じ武家社会で儀礼化された。もっとも古く文献に登場するのは、『軍用記』における「出陣の盃」である。これは、主従の間で武運を約する、という意であっただろう。
これが、庶民社会に伝わり、祝言(しゅうげん)の女夫(みょうと)盃となった。近年までは親子盃、兄弟盃なども広く伝えられてきた。とくに、ヤクザやテキヤなどアウトローの世界では、襲名盃が脈々と受け継がれてきた。映画のスクリーンで、それをご覧になった方も多いだろう。
なお、神人の間で取り交わす盃事もある。「直会(なおらい)」である。これも、祈願と加護の契約関係の成立を証すことにほかならないのである。 |