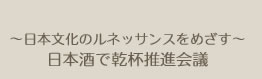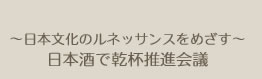|
京の都の「洛中洛外の酒」の中で、特に名声が高かったのが「柳酒(やなぎざけ)」であった。その醸造元は五条坊門西洞院にあり、門前に柳の木があったところから「柳の酒屋」と呼ばれていた。当時の京で最も繁盛しており、明徳四年(一三九三年)には、洛中洛外の酒屋の年間課役の一割以上の納銭(七百二十貫)を納入している。また法華宗妙本寺再興に際しては千貫文の奉加を行ったとの記録もあるので、相当に規模の大きな酒屋であったようだ。
これに次ぐのが五条烏丸(からすま)の「梅の酒屋」であり、文明一一年(一四七九年)には当時の将軍足利義尚がこの酒屋に臨んでいる。
とにかくこの中世というのは、寺院の酒造りとは別個のかたちで、利益を目的とした街の酒屋が次々と誕生した時代であったから、必然的にそこには経済戦争が発生してくる。たとえば「柳の酒」対「梅の酒」という名前の拡張の競争であり、品質の競いあいであり、価格の争いであった。
「柳の酒屋」は店の入口に大きな「六星紋」印の暖簾(のれん)を下げ、樽にもその印を書いて大きく「柳酒」と銘柄を入れたが、酒の銘柄(商標)が商品というはっきりとした目的で付けられたのはこのころが最初と考えてよいようだ。こうして酒屋は以後、製品に銘柄を付けるようになり、また消費者はこの銘柄を目安に、自分の好みの酒を選ぶという今日の形が出来上がった。
すると酒屋は、銘柄の名にかけて良い酒造りに精進し、酒質は著しく向上することになった。すなわち銘柄の登場は、酒造技術の発展にも大きな役割を果たし、その良酒醸造法は『酒造秘伝法』や『酒造肝要記』、『伊丹摂津満願寺屋伝』、『童蒙酒造記』といった酒造りに関する古文書を実に多く生むことにもなったが、これらの古文書は酒に銘柄が付きだした直後から激増している。
こうして次々に酒の銘柄が生まれ、それが「商標」として以後の人たちに親しまれてきた。今日、日本にある約一七〇〇の酒造会社には、一社平均七件の商標銘柄を持っているといわれているから、何と日本酒には一万二千を超す銘柄があることになる。
ところで、造り酒屋が酒の銘柄を決める場合は、この「柳酒」や「梅の酒」というようにその酒造家に因んだものもあるが、最も多いのは、今も昔も縁起のよい銘をつけるというものである。たとえば長寿の象徴の「鶴」の字をつけた酒銘は現在約二五〇もあって第一位、第二位が「正宗(まさむね)」(この「正宗」という字が酒の銘柄に多いのは、経文の「臨済正宗(せいしゅう)」の「正宗」が「清酒(せいしゅ)」に通じるからだというのは俗説で、刀でよくいう「名刀正宗(めいとうまさむね)」に由来しているからだと思われる。というのは、「切れ味」のすばらしい酒こそ名酒の条件だと昔からいわれているからである)、第三位が「泉」で、以下「桜」「川」「菊」「井」「山」「月」「花」「雲」「梅」「水」の順になっている。これらのキーワードを一つ決めると、その上下につける字は、字面や語感、そしてイメージからキーワードとピッタリと合うものを捜しだし、酒銘を決定するのである。正に日本酒の銘柄付けは、昔も今も浪漫に満ちたものであるのだ。 |